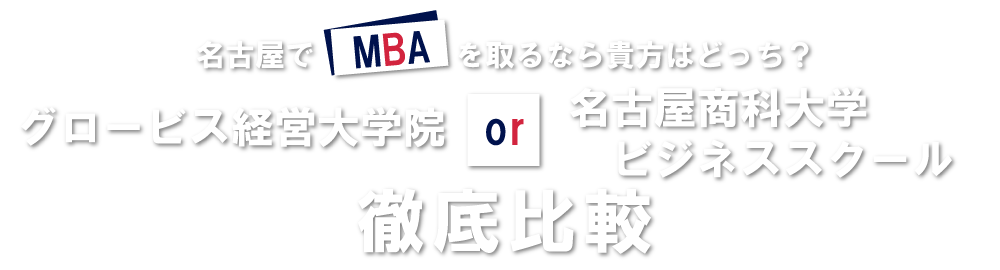リーダーシップとマネジメントの違いは?役割やスキルアップ方法
「リーダーシップ」と「マネジメント」の定義
日本では混同されがちな「リーダーシップ」と「マネジメント」。リーダーやマネジャーとして現在、組織をまとめる立場にある場合、「リーダーシップ」と「マネジメント」の違いを正確に理解できていなければ、今後の施策結果に大きな影響が出る可能性があります。
「リーダーシップ」と「マネジメント」の違いを知る上で、それぞれの定義を理解しておきましょう。
リーダーシップとは
企業や組織で決めた目標・目的の達成のため、集団活動に自ら進んで参加し、チームを導く能力のこと。また、組織・チームメンバーのビジョンを決め、集団活動の維持にも努めます。
リーダーシップに関しては、オーストリアの経営学者「ピーター・F・ドラッカー」や、「7つの習慣」の著者「スティーブン・R・コヴィー博士」などの多くの職者によって、さまざまな角度から定義付けられています。
その中でも、リーダーシップの基本的なポイントとしてあげられるのは、「ビジョン(方向性)」と「結果」です。目標や成果物を実現させるために、長期的な見通しや新たな挑戦、秩序の創造、オリジナリティ、人格者などの要素を持っていることが、リーダーの条件となります。また組織・チームリーダーとして、全体を導くスキルが求められます。
リーダーシップは、経営者をはじめ、新規事業のリーダー、あるいはリーダー候補といったポジションで求められる能力でもあります。
マネジメントとは
目標・目的を達成するために、組織やチームに必要な要素を分析・管理して、集団活動を維持・促進させる能力のことです。
行動や創造を司るリーダーシップと違い、マネジメントは目標・目的の達成のための、解決方法の模索・管理が主な役割となります。具体的には、組織のメンバー管理や短期的な見通し、前例を模倣、損得勘定、戦略立案、現状認識、秩序・規則の遵守などがあげられます。
つまりマネジメントには、組織を機能させる役目があるのです。またマネジメントは、企業の部長・課長などの管理職や、現場をまとめるマネジャーに必要な能力でもあります。
「リーダーシップ」と「マネジメント」の違い
リーダーシップは、どのようなビジョンに対して、どの方向にメンバーを導いていくのかという「定性的」な目標を定めます。そのため将来のビジョンや、長期的な視野で見る能力が必要です。
一方マネジメントは、いつ誰に対してどのように進めていくのかという「定量的」な目標を決めます。現実的で、短期的な視野で物事を考える力が求められます。
例えばリーダーシップでは、「将来的に自社のサービスが全国の企業に導入され、このサービスと言えば自社と言われるようなサービスのブランド化を目指す」というビジョンを定めたとします。この場合マネジメントとしては、そのビジョンを達成するため、「売り上げ目標1,000万円を突破するために、月100万円の売り上げを目標に営業をかける」というふうに具体的な計画を立てます。
「リーダーシップ」と「マネジメント」に必要なスキル
組織から期待されることは人によって違いますが、昇進・昇級のタイミングも人それぞれです。「リーダーシップ」と「マネジメント」では、求められるスキルも異なります。キャリアパスを構築するために、どのようなスキルが必要なのかを掴んでおきましょう。
リーダーシップに必要なスキル
リーダーシップを発揮するには、他のチーム・メンバーを先導する能力や、影響力が必要になります。これらの能力を持っている人には大抵、人間的な魅力が備わっているものです。
また、新たな目標や目的をチームのメンバーに示すためには、先見性が必要になります。時代や経済の流れを正確に読み取り、次にやってくる流行りやニーズを的確に見つけ出せる能力は、リーダーシップに必須のスキルといえます。
マネジメントに必要なスキル
マネジメントを行うには、「管理調整能力」が必要です。マネージャーには、現状の課題や問題を把握し、営業活動を維持する役割があります。目標を達成するための計画やタスクの洗い出し、組織能力の仕組み化、進捗管理、資源確保、チームの人員計算など、ロジカルシンキング(論理的思考)に基づいた「管理調整能力」が求められるのです。
リーダーシップに必須の条件
リーダーシップをとる方法には、人によってそれぞれ個性がありますが、リーダーシップをとる上で欠かせない要件というものがあります。
当事者意識
物事を進める上で必要な、使命感や責任感にもつながる要素で、リーダーシップを発揮する上で、当事者意識はバックボーンという位置付けになります。
自分がやらなければという自負や覚悟、決断力なども、当事者意識から生まれるものと言えます。
実行力
リーダーシップをとる際に優先されることは、熟考より「行動」することです。フットワークが軽いことは、リーダーの大胆さの源泉となります。部下へやらせる前に、まず自分が実践してみて、その姿を見せることでメンバーが感化され、そのほかのメンバーへと影響を与えていきます。組織の一員として受け身で命令を聞くのではなく、信頼感でリーダーについていくという、メンバーの自発性を促すきっかけになるのです。
チームで協力する意識
マネジメント寄りの意識としては、チーム全体で一つの目標を達成するとした場合、その目標をメンバー一人ひとりの目標へ細分化し、それぞれの進捗状況を管理することで達成につなげようと考えるでしょう。
リーダーシップの場合は、あくまでもチーム全体で目標を達成することにこだわります。そのために、どのような貢献が必要かをメンバーに求めます。リーダーは、メンバーの意欲を維持することに意識を集中し、自分自身が成果を上げようという考えは二の次にします。
パッション(情熱)
リーダーの強い思いの背景にパッションが感じられた時、メンバーは理屈抜きで動かされます。理屈でメンバーを動かそうとすれば、メンバー自身の理屈の範囲内でしか動こうとしません。しかし、そこにパッションが関わってくると、メンバーは理屈を超えてパワフルに行動し、できるだけチームに貢献しようとするでしょう。メンバーに損得勘定を持たずに動いてもらえるかは、リーダーシップが発揮できているかどうかの試金石ともいえます。
リーダーシップの素質
リーダーシップを発揮する上で、持っていると有利になる素質があります。決して、素質がなければリーダーシップを発揮できないというものではありません。こうした素質は、意識的に身につけることも可能です。
高い自己効力感
自己効力感は、ある状況下で「自分は必要な行動をうまくこなせる」と、自分の可能性について予期できることを指します。
リーダーシップをとる上では、この自己効力感が高いこともプラスになります。自己効力感の高さは、物事を始めようと思いついた際に、実際に行動へ移すかどうかに関わってきます。また物事を始めた後、継続的に行動できるか、困難に耐えられるか、といったことにも影響します。
自信のないリーダーについていきたいと思うメンバーはいないでしょう。自己効力感が高いことは、メンバーの意識を高めることにもつながるのです。
フェア
正義感が強く、考え方が公平で私心がない「公明正大」なリーダーは、メンバーからの信頼を集めます。また、リーダーのポジションを「特権」ではなく、「重大な責任感を伴う立場」と認識していることが、献身的な行動に現れるのです。こうしたリーダーの行動というものは、メンバーを感化させるために重要であり、リーダーシップの機能を向上させる結果となります。
ポジティブ
リーダーの前向きな発言は、メンバーにも好影響をもたらします。逆に、仕事に対する愚痴を言ったり、皮肉やからかうような発言をしたりするリーダーでは、メンバーのやる気が損なわれ、失望されてしまうことも。
どんな困難もポジティブにこなそうとするリーダーの姿勢は、メンバーから見ると、非常に頼れる存在となります。また好奇心旺盛でユーモアがあり、明るく、遊び心のあるリーダーとは、一緒に仕事をしたいと心から思えるものです。
成長志向
常に成長したいという志向を持つリーダーは、謙虚な姿勢でありながら、アグレッシブであることを望みます。自分に限界を決めず、目標達成のために、自分を超えることに意識を向けているのです。そうしたリーダーの姿勢は、メンバーにも刺激となって、チーム全体の成長をも促すことにつながります。
リーダーシップ力とマネジメント力を磨くには
スキルは後からでも身につけられる
リーダーとして人の上に立つ者としては、「リーダーシップ」と「マネジメント」の両方を兼ね備えているのが理想です。しかし、当然ながら人には得手不得手があります。
マネジメントに関しては、手法を学ぶことで、ある程度のスキルを習得できます。一方のリーダーシップに関しては、カリスマ性のような特性が必要なのではないかと考える方が多いですが、決してそのようなことはありません。リーダーシップは、リーダーのポジションに立ち、自身の立場を認識した時に、自然な動作として現れるものです。その後は自分の性質に合わせて、アプローチの仕方を選択し、スキルアップしていけば良いのです。
スキルを習得する方法
グローバル化された経済界で勝ち残るため、多くの組織では、研修や講座を行って、「リーダーシップ」や「マネジメント」のスキルの習得に力を入れています。自分が思い描くキャリアパスと、組織が求める役割とを比べ、会社が提供している研修・講座を利用すると良いです。
また、「マネジメント」と「リーダーシップ」に関して、より詳細な内容を効率よく学びたいのであれば、ビジネススクールで専門的に学ぶと良いでしょう。
ビジネススクールでは、さまざまなセッションを通じて、リーダーやマネジャーが、どのような取り組みを行えば良いのかについて、フレームワークを活用して、考える力を磨いていけます。
自分の可能性を広げる「MBA」を学ぶ
幅広いビジネススキルを学べることはもちろん、年収アップや転職にも有利になる「MBA」。
当サイトでは、名古屋でMBAを取得できる2校「グロービス経営大学」と「名古屋商科大学ビジネススクール」を徹底比較しています。
学べる内容やスクール選びのポイント、MBAを取得するメリットなどを、ぜひチェックしてください。